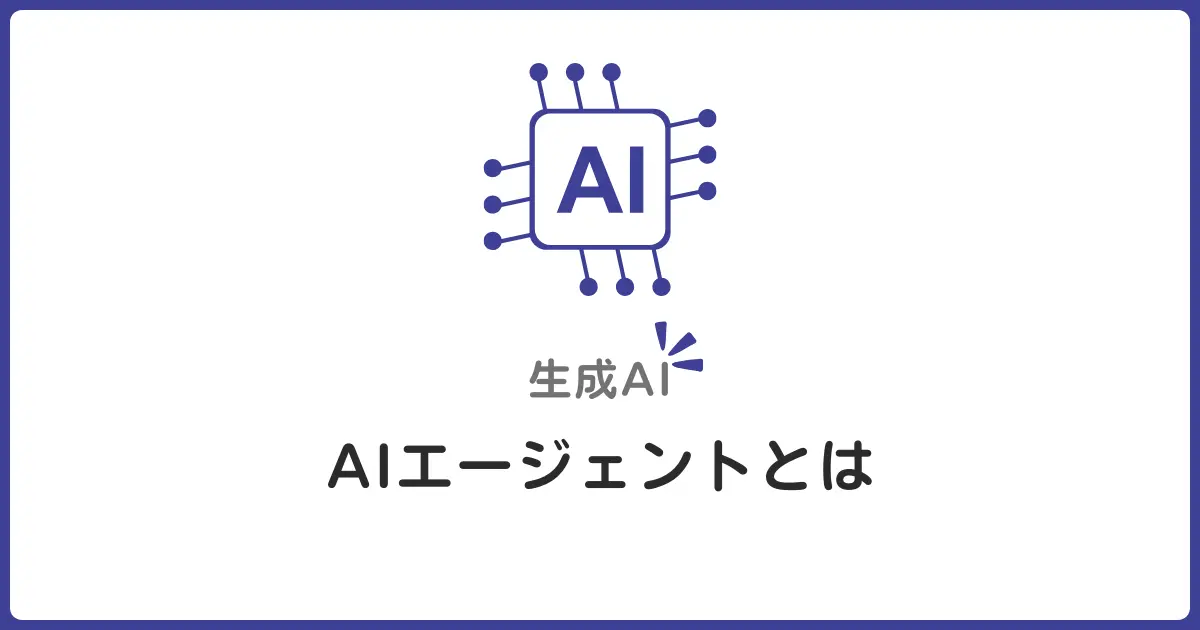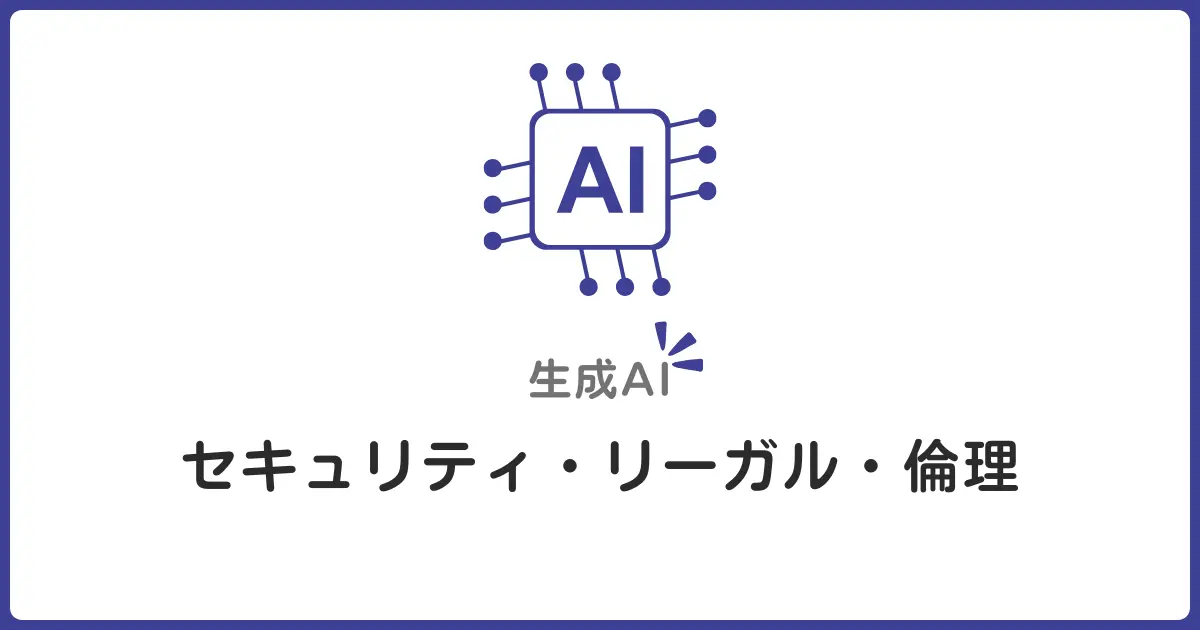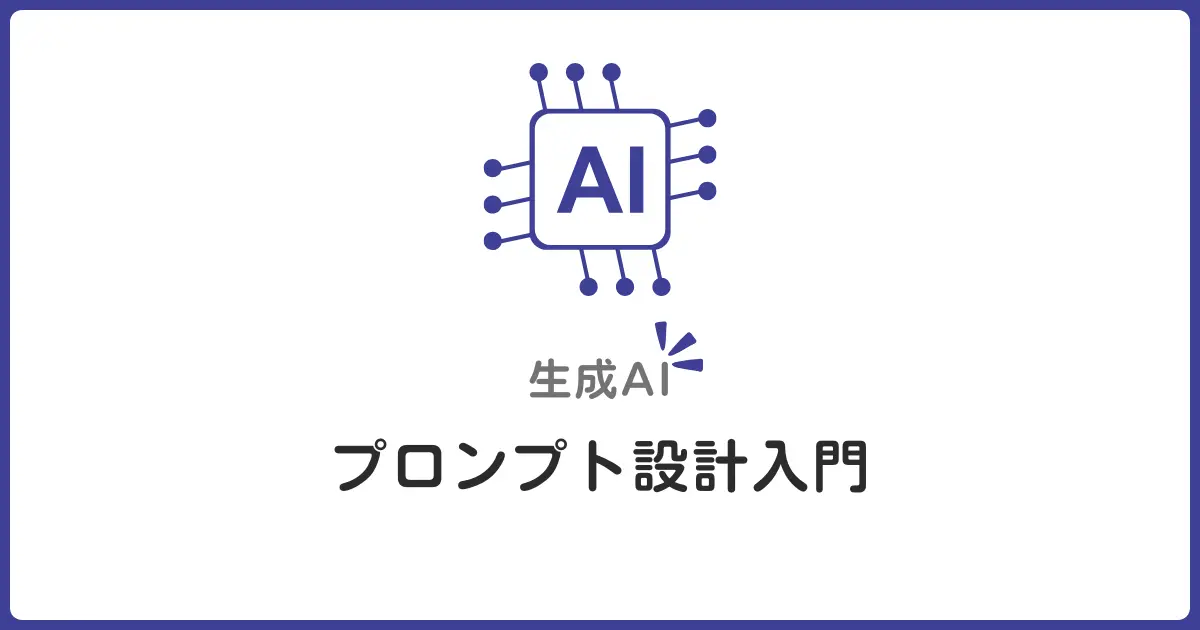リンドくん
先生、最近AIツールがたくさん出てるみたいですけど、どれを使えばいいのかわからなくて...
たなべ
確かにAIツールはたくさんあるよね。でも今回紹介するAmazonの「Kiro」は、他のツールとは全く違ったアプローチを取っているんだ。
従来の「なんとなくコードを作る」スタイルではなく、しっかりとした要件定義から始めるという、本来あるべき開発プロセスをAIがサポートしてくれるんだよ。
プログラミング学習を進めていると、「とりあえずコードを書き始める」という習慣がついてしまいがちではないでしょうか?
実はこれ、多くのプログラマが陥りがちな落とし穴なんです。
プロの開発現場では、まず「何を作るのか」を明確にしてから開発を進めるのが基本的なプロセスです。
この記事では、Amazonが2025年7月に発表したAIエージェント型IDE「Kiro」について、実際に使ってみた感想をお伝えします。
このツールは従来のAIコーディングツールとは一線を画す「スペック駆動開発」という手法を採用しており、初心者の方にこそ使ってほしい革命的なツールなんです。
↓YouTube版はこちら
Kiroとは?従来のAIツールとは何が違うのか
「Vibe Coding」から「Viable Coding」への転換
Kiroの最大の特徴は、その設計思想にあります。
多くのAIコーディングツールが「Vibe Coding」、つまり「なんとなくそれっぽく作る」というスタイルを採用している中で、Kiroは「Viable Coding」(実行可能であることを最優先にする)という考え方を徹底しています。
具体的には以下のような流れで開発を進めていきます。
- 要件定義 → 何を作るのかを明確に決める
- 設計フェーズ → どのような構造で作るかを設計する
- タスク分解 → 実装すべき項目を細かく分ける
- 実装 → 計画に沿ってコードを生成する
この流れは、まさにプロの開発現場で行われている正しいプロセスそのものです。
スペック駆動開発のメリット
Kiroが採用している「スペック駆動開発」には、以下のような大きなメリットがあります。
- 方向性の間違いを防げる → 明確な要件定義により、開発の途中で迷子になることがありません
- ハルシネーション(AI特有の間違い)を抑制 → 存在しないライブラリやメソッドを使用するリスクが大幅に減ります
- 透明性の確保 → 何をしているかがすべて可視化されるため、安心して使えます
従来のAIツールでは、時々とんでもない方向に進んでしまったり、実際には存在しないコードを生成してしまったりすることがありましたが、Kiroはタスクを明確に分解することで、こういった問題を防いでくれるんです。
Kiroの基本的な使い方と実践
リンドくん
実際にはどうやって使うんですか?難しそうで不安です...
たなべ
心配しないで!Kiroは「Kiroのやり方に合わせて進めてね」というスタンスを取っているから、むしろ初心者にとっては使いやすいんだ。
正しい開発プロセスを自然と身につけられるからね。
インストールと初期設定
現在Kiroは2025年7月現在、パブリックプレビュー期間中のため基本的には無料で使用できます。
ただし、予想以上の注目を集めたため、現在はWaitlist(待機リスト)への登録が必要な状況です。
対応プラットフォーム
- Windows
- macOS
- Linux
アカウント登録方法
- Googleアカウント
- GitHubアカウント
- AWSのBuilder ID
- SSO
開発者の多くがすでに持っているアカウントで登録できるため、セットアップの敷居は低くなっています。
メイン機能の紹介
Kiroには以下の主要機能があります。
1. Specs(スペック機能)
要件定義を行うKiroの心臓部と言える機能です。ここで「何を作るのか」を明確に定義します。
2. Agent Hooks
指定の行動をトリガーにイベントを発生させる機能です。例えば「コードを保存した後にLinterを実行して」といった自然言語での指示が可能です。
3. ステアリング
プロジェクト全体のルールや構造、コーディング規約を定義するためのドキュメントを生成する機能です。
4. MCP設定
外部ツールとの連携設定を行える機能です。
他のAIツールとの比較
CursorやWindsurfとの違い
現在人気の高いAIコードエディタであるCursorやWindsurfと比較すると、それぞれに特徴があります。
Cursor
- 長所: コード生成速度が高速、多様なモデルに対応
- 短所: ユーザーの指示出しスキルに依存する部分が大きい
Windsurf
- 長所: 対話型エージェントとして文脈理解力が高い
- 短所: 複雑な要求の段階的な伝達が必要
Kiro
- 長所: スペック駆動開発により、初心者でも正しいプロセスを学べる
- 短所: 現状では対応モデルが限定的(Claude Sonnet 4.0、3.7)
使い分けの提案
自分としては、以下のような使い分けがおすすめです。
- 開発初期段階 → Kiroで要件定義と基本設計
- コード生成段階 → Claude CodeやCursorでざっくりとコード作成
- 微調整段階 → GitHub Copilotで細かい調整
このように、各ツールの強みを活かした組み合わせで使うことで、より効率的な開発が可能になります。
Kiroを使うべき理由とメリット
リンドくん
結局、Kiroを使うとどんなメリットがあるんですか?
たなべ
一番大きなメリットは、正しい開発プロセスを自然と身につけられることだね。
多くの初心者が「とりあえずコードを書く」という習慣を避けて、まずは何を作るのかを明確にしてから開発を進めるという正しいプロセスを学べるんだ。
プログラミング学習者にとっての価値
1. 正しい開発プロセスの習得
要件定義→設計→実装という流れを自然と学べるため、将来的にチーム開発に参加する際にも役立ちます。
2. 安全性の高いAI活用
初めてAI系IDEを使う人にとって、比較的安全性が高い状態でAIの力を活用できます。
3. プロダクト開発への応用
実験的なツールではなく、実際のプロダクト開発で使えることを前提とした設計になっています。
エンジニアにとっての価値
1. プロジェクト管理の効率化
コードを書くことよりも、プロジェクト全体を管理することに重点を置いた設計は、特に大規模な開発プロジェクトで威力を発揮します。
2. ドキュメント生成の自動化
ステアリング機能により、プロジェクトの概要、構造、技術スタックに関するドキュメントが自動生成されます。
3. チーム開発での標準化
明確な要件定義と設計ドキュメントにより、チーム内での認識統一が図りやすくなります。
まとめ
Kiroは単なるAIコーディングツールではありません。
プログラミングの正しいプロセスを学ぶための教育ツールとしても優秀な存在です。
従来のAIツールが「速くコードを書く」ことに重点を置いていたのに対し、Kiroは「正しくコードを書く」ことを重視しています。
この違いは、特にプログラミング学習者にとって非常に重要な意味を持ちます。
現在はWaitlistへの登録が必要ですが、まだ登録していない方はぜひ登録してみてください。正式リリース時には、さらなる機能向上が期待できそうです。
Kiroのようなツールを活用することで、AIの力を借りながら正しい開発プロセスを身につけ、より良いエンジニアを目指していきましょう!